知らざれる木の世界
- ptakuyap15
- 2023年2月10日
- 読了時間: 5分
更新日:2023年2月17日
当たり前のようにいつもわたしたちの側にいる木。 あなたは木についてどれくらい知っていますか? 木が社交的な生き物だと言ったら、 木がお互いコミュニケーションをとると言ったら、 あなたは信じますか?
Peter Wohllebenさんが書いた「The Hidden Life of Tree 」という本を元にシェアします。

木は社交的な生き物である
人間や他の動物が単独では生きていけず助け合って生き延びる集団な生き物であるように、木もお互い支え合って生きてきた集団の生き物なのです。
地面の中で根っこ同士がアリの巣のように繋がっている。登山をしていると元々は土で隠れていたこの部分が雨で剥き出しになってしまった様子を見たことがある人もいるかもしれません。
なぜ木は他の木を助けるのか?それは私たちと同じ理由です。お互い助け合った方が皆が生き延びていく上で有益だからです。
木一本だけでは雨や台風から自分を守ることができませんが、複数の木は(森や林)は防ぐことができます。また木が集団に集まることによって熱や湿気を保つことができ、皆によって心地の良い環境を作りだすこともできます。
さらに驚きなのが、周りの元気な木だけではなく、ダメージを受けて弱ってしまった仲間を助けるということです。
著者が森の中を散歩中にとても古い切り株を見つけたそうです。切り株の内側は腐れかけていたことから400年も切り倒された切り株だということが分かったそうなのですが、外側はしっかりと生き延びていることが確認できたそうです。
なぜ倒れた木が生き延びることができたのか?倒れた木には光合成に必要な葉っぱが残されていません。
同じような状態の切り株を調べた科学者たちによると、周りの木々が根っこを通してこの切り株に栄養を送っていたということを発見したそうです。
木のコミュニケーション方法
そんな社交的な生き物であるのであれば、お互いにコミュニケーションをする術が必要です。
木々はいったいどうやってお互いにコミュニケーションを取り合っているのでしょうか?木の言語というものが存在するのでしょうか?
一番のコミュニケーション方法は匂いです。
多くの科学者は私たち人間も汗という匂いがパートナーを選ぶ上で大きな要因となっていると信じています。
同じように、木にとっても匂いという言語は大きな役割を果たしているのです。
アフリカのサバンナでキリンがアカシアの木の葉っぱを食べていました。
キリンが葉を食べ始めて数分後にアカシアの木は葉っぱから毒素を抽出し、キリンをおっぱらったのです。
さらに驚きなのは、木は受けた接触ごとに異なる反応をとることができるということです。
つまりはどんな虫が自分に攻撃をしているのかを木は識別することができるのです。
虫それぞれの唾液は違うので、木は唾液をもとに虫を識別します。
なので自分に害のない虫を匂いを使って呼び寄せて、その虫に害を与える昆虫を攻撃させることによって自分の身を守るのです。
それだけではなく、エタノールガスを放出して100m圏内のアカシアの木にキリンから身を守るようにメッセージを送ったのです。
このメッセージ(ガス)を受けた周囲のアカシアの木は瞬時に葉から毒素を抽出して、キリンから身を守ったのです。
木が匂いという言語を使うのは、身を守るためだけではありません。
柳の木やキンモクセイなど、散歩をしているとついうっとりしてしまう香りを放出する木があります。
こういった木は香りを放出することで、受粉を助けてくれるハチを引き寄せているのです。
木の相棒
木が生き延びていく上で、成長を続けていく上で光と同じくらいかかせないのが水です。
地面下でさらに水を吸収していく上で木の欠かせない相棒となっているのが、フンギです。
動物とも植物とも言えないフンギは地球上でとってもユニークな生き物です。
フンギが地面下で作る集合体はmycelium(マイシリム)ともよばれ、どんどんと拡大をしていくものです。
ちなみに、アメリカのオレゴン州では世界最大の菌類と想定される生き物がいます。2,400歳と推定される、なんと3.8km以上に渡って発生し、9.65平方キロメートル(2,385エーカー)を占めるといわれています。
関西国際空港の敷地面積が約10.58平方キロメートルだというから、その大部分が覆われてしまうサイズになってしまいます。
ちなみにこの巨大生物は木に対してフレンドリーではないようです。
では、フレンドリーな木とフンギの関係とはどのようなものなのでしょうか?
相性の良い木とフンギが協力することによって、機能的な根っこの表面を増やすことにより、より多くの水分と栄養を吸収できるようになります。
フンギと協力していない木と比べると、およそ2倍の量といわれています。
フンギの菌糸は木の根っこの毛のように細い先端から、木の中へと入っていきます。
木に入り込んだフンギは、地面かどんどんと広がり蜘蛛の巣のように菌糸のネットワークを広げてゆき、遠くの木とも菌糸を通して繋がっていきます。
そうすることで、離れた木同士もお互いに栄養素を送り合うことができるようになるのです。
栄養素だけではなく、外部からの攻撃があった、などの情報も送り合うことができるようになります。
では、フンギは木から何をもらっているのか?タダ働きをしているのでしょうか?
フンギは代価として糖質を木からもらいます。
フンギは要求の強い相棒でもあり、木が生産する糖質の合計のおよそ3分の1もの量を要求します。
糖質という代価の代わりにフンギは木にとって有害になりうる鉄分をろ過して取り除いたりもします。それだけではなく、木にとって有害な菌類を追い払ったりもしてくれます。
木とフンギはうまくいけば何百年も一緒に生きていくことができますが、環境の変化などでフンギにとって有益でなくなると、フンギは他の木を探しに去ってしまいます。
またフンギは木だけではやり遂げることができない、思い切った行動もとることができます。
土の中の窒素の量が必要な量以下になってしまった場合、ある種のフンギは毒を放出して地面にいる微生物を殺します。死んでしまった微生物に死体から窒素が放たれ、この窒素を木とフンギが吸収するのです。



















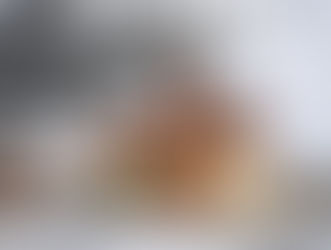







コメント