鳥に餌を与えるべきか?:自然のバランスに挑む私たちの選択
- ptakuyap15
- 2024年10月30日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年9月14日

Michalina AleksandrowiczによるPixabayからの画像
人間が自然界に手を加えることは、長い目でその影響を考えるとあまりよいことではないと考えられることが多いです。
特に、鳥の餌場を通じて野鳥に餌を与える行為は、想像以上に自然環境や生態系に影響を与えるものです。
とはいっても、かわいい鳥が餌をつつく様子を見ると、誰しもが鳥に対して愛嬌を覚えるものです。
このジレンマを、『The Weather Detective』の著者であるピーター・ヴォールレーベン氏の観察に基づいて考えてみましょう。
自然界の淘汰と生き残るための進化

Willfried WendeによるPixabayからの画像
地球上のすべての生き物は、生き延びるための闘いを通じて自然の変化に対応してきました。
例えば、冬の寒さや食糧不足などの厳しい環境は、健康で強い遺伝子だけが生き残る「自然選択(Natural Selection)」のプロセスを促してきました。
このようにして、より適応力のある個体が次世代に引き継がれ、不健康なDNAが自然に排除されていく仕組みです。
しかし、バードフィーダーによって人間が餌を与えると、これが崩れてしまう可能性があります。
例えば、通常、鳥の赤ちゃんのうち80%は夏まで生き残れないのが一般的です。
そのため、親鳥はリスクを考慮して複数の雛を育てます。ところが、餌場を設置して食べ物を提供すると、より多くの雛が生き残ることが可能になります。
その結果、春にはその地域である特定の鳥の数が増えすぎ、他の種の鳥が繁殖するための領域が不足する問題が生じることがあります。
また、鳥の餌場を設置したことがある人は毎日同じ鳥が餌場にやってくることに気づいたかもしれません。
鳥の餌場で食事をするのは、主にその土地の固有種に限られる傾向も問題点の一つです。
これにより、特定の鳥が多くなりすぎると、生態系全体のバランスが崩れ、他の種が生き延びるためのリソースが減少するというリスクも出てきます。
鳥の餌場がもたらす影響と利点

一方で、バードフィーダーを設置することにはメリットもあります。
普段は見ることができないような珍しい鳥を観察できるチャンスが増えたり、自然を身近に感じることができるからです。
特に子どもがいる家庭では、鳥たちの姿を毎日見ながら、自然界に対する理解や愛情を深める貴重な機会になるでしょう。
しかし、春の間は種間の自然な競争に影響を与えないよう、餌を与えないことが推奨されています。そうすることで、鳥たちが持つ自然のサイクルを尊重することができます。
取り残された鳥や動物の子供に手を差し伸べるべきか?

mgnorrisphotosによるPixabayからの画像
道を歩いていると、飛べなくなった鳥の子供や取り残された鹿の子供を見かけることがあります。助けてあげたくなるのは自然な感情ですが、これも慎重に考えるべきです。
自然界では、弱い個体が排除されることにより、強い遺伝子が残されていきます。ピーター・ヴォールレーベン氏が述べているように、人間が安易に介入することで、この自然の秩序に逆らってしまうリスクもあります。
鳥の子供に関しては、体が大きければ親鳥が戻ってきて餌を与える可能性が高いため、そのままにしておくのが賢明です。
しかし、頭が禿げていて羽毛に包まれているような小さな雛であれば、巣に戻すなどの助けが必要な場合もあります。
また、哺乳類の場合、親はほとんどの場合戻ってきますので、2〜3時間ほど待ってみるのが良いでしょう。それでも親が現れない場合は、助けを検討しても良いかもしれません。
ただし、取り残された動物は病気や怪我をしていることが多いため、人間が関与すると自然の淘汰のプロセスを妨げることになります。どうしても必要な場合に限り、怪我をしている、あるいは親が戻れない状況が明確な時に助けるべきだと理解しておきましょう。
日本でバードフィーダーが広まっていない理由

Sofia TerzoniによるPixabayからの画像
日本でバードフィーダーの設置が少ない理由は、いくつかの要因が絡んでいます。
まず、バードウォッチング愛好者が少ないことが影響しています。アメリカやイギリスに比べて、人口あたりの野鳥観察団体会員数が非常に少なく、自然に親しむための給餌も定着しづらくなっているのです。
また、日本では野鳥観察には費用をかける傾向が見られる一方で、給餌への関心が低いことが、観察用品と給餌用品の購入データからも明らかになっています。
さらに、日本独自の文化的背景もあります。自然に手を加えないでおくという意識が強く、野生動物に餌を与える行為を「不自然」と捉える傾向があるため、給餌を積極的に行う人が少ないのです。
また、日本の住宅事情も影響しています。庭が狭い、隣家が近いといった環境により、庭先での給餌が周囲に迷惑をかける懸念が生まれやすいのも一因です。
こうした要因が重なり、日本では野鳥への給餌文化が他国ほど広がりにくい状況にあります。
さいごに
鳥の餌場のジレンマや助けを必要とする動物への対応について考えることで、私たちは自然の一部としてどのように行動するべきか、改めて見つめ直すきっかけとなります。ピーター・ヴォールレーベン氏の『The Weather Detective』は、私たちが普段見落としがちな自然界の複雑な仕組みを教えてくれる一冊です。


















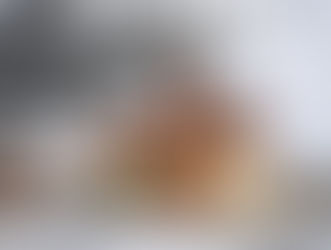







コメント