内なる静けさがもたらす生産性の向上と幸福感:現代社会での実践法
- ptakuyap15
- 2022年3月21日
- 読了時間: 16分
更新日:2024年8月21日

現代社会は常に情報と刺激に満ち、私たちはその中で生産性や幸福感を追い求めています。しかし、その喧騒の中で見落としがちな「内なる静けさ」が、実は本当の幸福感や生産性の向上に繋がることをご存じでしょうか?
このブログでは、ジョン・F・ケネディの冷静な判断からライアン・ホリデイの「Stillness is the Key」まで、静けさが私たちの生活にどのように影響を与えるのかを深く掘り下げます。忙しい日常の中で、いかにして静けさを実践し、内なる平穏を取り戻すことで、仕事の生産性や幸福感を高めることができるのかをご紹介します。
あなたがリモートワーカーでも、忙しいビジネスマンでも、心の静けさを実践することで得られる恩恵を知り、実生活に役立ててみませんか?このブログでは、実践的な方法や成功事例を通じて、現代社会で内なる静けさを取り入れるためのヒントをお届けします
目次:
”静けさ”がなぜ重要なのか?
1962年、アメリカ大統領ジョン・F・ケネディは、ソビエト連邦がキューバにミサイル基地を設置し、アメリカ本土に向けてミサイルを発射する準備をしていることを知りました。この事態は、アメリカのみならず、世界全体が核戦争の危機に直面する「キューバ危機」として後に知られることになります。
多くの政治家や軍のアドバイザーたちはケネディに対し、「今すぐにミサイル基地を攻撃すべきだ。一刻を争う状況だ」と強く訴えました。誰もが迅速な軍事行動を求めていましたが、その緊張感の中で、ケネディがとった行動は意外なものでした。彼はホワイトハウスの庭を静かに歩きながら、じっくりと考える時間を取ったのです。
この13日間の緊迫した状況の中、ケネディの冷静な対応が結果的に核戦争を回避し、世界を救いました。彼の「静けさ」がこの危機を乗り越える鍵となったのです。
人類の歴史を振り返ってみても、このように「静けさ」が多くの命を救ってきた例は数多くあります。激流の中に静かに立つ岩のように、揺るぎない静けさこそが、私たちの幸福への鍵となり得るのです。『Stillness is the Key』の著者ライアン・ホリデイは、この静けさが現代社会においてますます重要であると説いています。
想像してみてください。あなたが家族と一緒にリラックスして過ごしている時間、何も言わずに静かにしていると、わずか数秒で「どうしたの?」「何かあったの?」と心配されることがあるかもしれません。じっとするという行為は本来簡単なはずなのに、なぜ現代社会ではこれが難しく、異常な行動と見なされるのでしょうか?
それは、私たちが常に電話やメール、SNSといった外部からの刺激にさらされているからです。スマートフォンを開けば簡単にドーパミンが得られ、街を歩けば次々と物欲を刺激する広告が目に入ります。こうした環境の中で、私たちは自分を他人と絶えず比較し、静けさを失っているのです。
このような現代社会で生きる私たちにとって、静けさを取り戻すことがどのように幸福への鍵となるのでしょうか?静けさは、私たちが内面と向き合い、本当の自分に気づくための時間を提供してくれます。外部の喧騒から離れ、心の静寂を保つことが、真の幸福を手に入れるための道筋なのです。
私が考える”静けさ”の魅力
リモートワークでの「静けさ」の力
私はリモートワーカーとして、仕事に集中するためにさまざまな方法を試しています。たとえば、疲れてきたときには、アップテンポな音楽を大音量で聴いたり、コーヒーなどのカフェインを摂ったり、普段と違う場所に移動してみたり、立ちながら仕事をしたりといった工夫をしています。これらの方法は一時的には効果があり、集中力を高めてくれます。
しかし、これらの「ブースト」は長続きしません。いわゆる「ドーパミンラッシュ」が切れると、再び集中力が低下してしまうのです。
これとは対照的なのが、音楽もかけずにじっと椅子に座り、淡々とパソコンに向かって仕事をする、いわゆる「静けさ」の状態です。振り返ってみると、一番多くの仕事をこなすことができたのは、実はこの「静けさ」に包まれたときでした。
この「静けさ」は単なる生産性の向上だけでなく、「満足感=幸せ」にもつながっています。もしかすると、これは心理学で言う「フロー」の状態かもしれません。(*フローについては、過去のブログ「WHY I HIKE」で詳しく説明しています。)
私が考えるに、この「静けさ」をデフォルトの状態にできれば、まさに最強なのではないでしょうか。イメージとしては、川の流れに動じない、どっしりとした岩のようなものです。外部からのシグナルや情報に反応せず、淡々と仕事をこなす。そうすることで、1日8時間の仕事時間を効率的に使い、それ以外の時間を存分に楽しむことができるはずです。
心の平穏
「Your thoughts create your reality.(思考が現実を創り出す)」という言葉をよく耳にします。同じ環境にいても、感じ方や捉え方次第で世界は全く異なるものに見えることがあります。
たとえば、友人とハイキングをしていたときのことです。突然雨が降り始め、私は「最悪だ…」とつぶやきました。しかし、一緒にいた友人は、ジャケットも着ずに笑顔で雨を楽しんでいる様子でした。「雨に濡れながらハイキングをするのが楽しい!」と。
最初は「何を言っているんだ?」と思いましたが、騙されたと思って彼のように楽しんでいるふりをしてみました。すると、不思議なことに、雨が嫌なものではなくなってきたのです。雨が地面や木々に当たる音が、どこかリラックスできる音にさえ聞こえてきました。
この本では、「静けさ」を身につけるために行うべきことを、大きく3つのドメインに分けて説明しています。
1. Mind(メンタル)
2. Spirit(エモーション)
3. Physical(ボディ)
Mind: マインドを空っぽにする
冒頭のキューバ危機におけるジョン・F・ケネディの話に戻ります。彼は、極度のストレスがかかる状況で、どのように「静けさ」を保ち続けたのでしょうか?
ケネディのオフィスから見つかった一枚の白い紙には、彼が繰り返し書いた「missile, missile, missile」と「consensus, consensus, consensus」という言葉が残されていました。これは、頭の中にある考えを紙に書き出す「モーニングページ」と呼ばれるエクササイズに似ています。
モーニングページとは、毎朝、頭に浮かんでくることをただひたすら紙に書き出すことで、マインドを空っぽにするエクササイズです。意味不明なことでも構いませんし、文章になっていなくても問題ありません。ただ、心の中の雑念を文字にして吐き出すのです。
私自身もこのエクササイズを実践しています。考えや悩みを書き出すことで、気持ちが整理され、前向きな姿勢になることが多いです。書いている途中で解決策が浮かぶこともあります。このエクササイズは、朝一に行う人もいれば、夜寝る前に行う人もいます。
Become Present: 今を生きることで幸福感アップ
「Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present.」(昨日は過去、明日は未来、でも今日は贈り物。だから「プレゼント」と呼ばれるのです。)- ビル・キーン
自然の中をハイキングしているとき、スマホで友達とビデオ通話をしながら歩いている人を見かけたことがあります。広大な自然に囲まれているにもかかわらず、なぜ今この瞬間を楽しもうとしないのか?と疑問に思うことがあるかもしれません。
次のシチュエーションも同様です。久々に友達と会話している最中、スマホに通知が来て、ついインスタグラムを開いてしまい、そこから友達の話に全く集中できなくなった経験はありませんか?これらは、どちらも「mind」が現在から離れてしまっている例です。
また、新しい環境や仕事を始めたときに、過去の写真を見ながら「あの頃は良かったな…」と思い出に浸ることもあるでしょう。これは一見普通のことのように思えますが、現在のチャンスを見逃すリスクもあります。人は過去を美化する傾向があるため、現在の状況を正しく評価することが難しくなるのです。
さらに、新しい家に慣れ始めた頃、雑誌やインターネットで新しい魅力的な家を見つけ、「今度はこの家が欲しい」と感じることもあるでしょう。そんなときには、「今の家も、かつて自分が切望していたものだ」と思い出してみましょう。
では、「present(今)」を生きるためにできることは何でしょうか?
最もシンプルでありながら難しい方法は、瞑想です。無の状態に入り、自分の呼吸や思考を観察することを通じて、現在に集中します。また、何か挑戦的なことに取り組むことで、他のことを考える余裕をなくすのも一つの方法です。
YouTuberのCasey Neistatは、ポッドキャスト「Steve-O’s Wild Ride! EP #54」で、ニューヨークでのハードワーク時代と、ロサンゼルスで家族や友人との時間を大切にするようになった時代について語りました。
彼はニューヨーク時代、すべての行動基準が「Vlogに使えるかどうか」に左右されていたといいます。友達からの誘いも、「このシーンが使えるか?」と考え、使えないと判断すれば断っていたそうです。
しかし、このような生活では、家族や友人との関係に支障が出ることに気づき、ロサンゼルスに移住しました。そこで彼は、サーフィンを楽しむようになったと話します。サーフィンはカメラを持ちながら行うことが物理的に不可能なので、完全に「今」に集中できるのです。
このように、サーフィンのように「今」に集中せざるを得ない活動を取り入れることは、現代社会において「present」を生きる良い方法です。
なお、2022年9月にCaseyは家族と共にニューヨークに戻ることを発表しました。彼自身も、妻も、ニューヨークという街を恋しく思い、再びこの街で「Work」と向き合う決意をしたのです。今回は、過去の経験を踏まえ、どのようにバランスを取るのかが興味深い点です。
私自身、何事も「足らずを知らずに足るを知ることはできない」という考えに共感しています。空腹を知らない人が満腹を本当に理解することは難しいですし、寒い冬を経験しない人が暖かい気候の喜びを理解するのも難しいでしょう。Caseyのように失敗や経験を通じて、自分の本心に耳を傾け、行動を起こすことが大切なのではないかと感じています。
Spirit: 自分独自の道徳的規範を持つ
「ルール」と聞くと、自由を束縛されるようなマイナスのイメージを持ちがちです。しかし、道徳的規範を持たない生き方は、何が正しいか悪いかの判断基準を持たずに生きることを意味します。
例えば、ちょっとした不正で利益を得るチャンスや、嘘をついて得をしようとする機会が訪れるたびに迷うことになるでしょう。これは、誘惑に振り回される「奴隷」のような状態です。
道徳的規範がなければ、行動が無意味に感じられがちです。例えば、お年寄りに席を譲る行動も、「他者に親切である」という規範がなければただの行動に過ぎません。牛乳パックをリサイクルすることも、「環境に優しくある」という基準がなければ価値を感じにくいでしょう。
日本では、小学校で道徳の授業があり、これが社会全体に道徳的な行動を浸透させているのかもしれません。レジでの割り込みが少ないのもその一例です。
では、あなた自身の道徳的規範を考えてみましょう。私の場合、「常に誠実であること」「人に親切であること」「ポジティブでいること」を大切にしています。この規範のおかげで、迷わず財布を交番に届けたり、たとえ相手を傷つける可能性があっても正直に話すことができます。こうした基準があれば、行動に迷うことが少なくなります。
「静けさ」を身につけたいのであれば、道徳的規範を持つことが必要です。また、自分の規範を他人に公表することで、より行動に一貫性が生まれ、悩むことが少なくなるかもしれません。例えば、
• 「午後6時以降は家族の時間なので、メールには返答しません」
• 「メッセージの即返信はしません」
• 「体が資本なので、睡眠と運動を最優先します」
このように規範を明確にすることで、他者が期待することと自分の行動が一致し、人生がシンプルになるかもしれません。
足るを知る
「Catch 22」の著者ジョセフ・ヘラーと彼の友人であるカート・ヴォネガットが、ある大富豪のパーティーに出席した際、カートがジョセフにこう尋ねました。
「このホストは、君の一番の成功作『Catch 22』の累計売上を1日で軽々と超える収入を得ているけど、どう思う?」
ジョセフはこう答えました。「確かにそうだが、僕は彼が一生かけても手に入れられないものを持っている。それは、足るを知ることだ。」
この言葉は、英語で「ENOUGH」に相当します。
現代社会では、「最新のiPhoneを手に入れたら幸せになれる」「ハワイに移住すれば幸せになれる」「部長になったら幸せになれる」「もっと魅力的なパートナーがいれば幸せになれる」と、次から次へと新たな欲求が生まれます。
最近、ピクサーの映画『ソウルフル・ワールド』を観ました。この映画には非常に深いメッセージが込められており、足るを知ることの重要性を教えてくれます。
夢見る音楽教師のジョーは小さな頃からプロのジャズミュージシャンになることを夢見ていました。
映画は、生まれる前の魂(ソウル)達の世界と私たちの世界を舞台に進んでいきます。
作中、プロのジャズミュージシャンになることがJoeにとってどれだけ大切で重要なことなのかが描かれています。。これなしだったら生きていく意味がない。とまで断言していました。
映画後半で、やっとの思いでジョーは念願のプロミュージシャンとしての舞台に立つことができます。
演奏が終わったあと、観客はスタンディングオベーションで大成功に終わります。
ショーが終わった後、最後にジャズバーを出るJoe。どこか困惑した表情をしています。
「So...What's now? 」と彼をプロジャズバンドに招待してくれた有名ミュージシャンに聞くJoe.
「また同じパフォーマンスを明日も、その次も繰り返すだけだよ」との返事。
ー
どんな人も「これを成し遂げれば絶対に幸せになれる!」という出来事が終わったあとの
想像とかけ離れた虚しさを感じた経験があるのではないでしょうか?
「Soul」の作中でも後にJoeが気づくように
カフェから出た時に季節の移り変わりにうっとりしたり
床屋のおじちゃんとおしゃべりしたり
成功・失敗・ドキドキすること・悲しいこと
自分が既に持っている日常の些細なことを経験し心から感じること
これこそが幸せに生きるために必要な姿勢なのかもしれません。
逆を言うと
〇〇さえあれば幸せになれる
〇〇になればきっと幸せになれる
といった考えは、あなたをそのこと以外のことに対して盲目にさせてしまう危険があります。
足るを知る。
今自分が持っていることに満足する・感謝する姿勢を身につけていきたいですね。
PHYSICAL
いらないものはもたない
あなたが仕事を頑張ってきた甲斐が報われ、昇進し給料がアップすることになりました。
一人暮らしのあなたはお金に余裕ができることになるので、親友の家のようにちょっと大きなアパートに引っ越すことに決めました。
今までは1Kに住んでいましたが、1LDKへランクアップ!
余分に部屋一つ増えたので、ソファーやテーブル、音楽スピーカーなど家具を購入しました。
とてもワクワクして住み始めたのですが、住み始めて数ヶ月後あることに気づきました。
ソファーがある新しい部屋はほとんど使わない、そのくせ掃除機はかけないといけない。
前回の狭いアパートより、エアコンでアパート全体が涼しくなるのに時間がかかる。
しまいには新しく買ったスピーカーが壊れてしまい、その修理をするためにスピーカーを店頭まで持っていかないといけない。
などなど、アップグレードをしたはずなのに、返って自分の人生が惨めになっていたのです。
このような経験を誰しもがしたことがあるのではないでしょうか?
More money, more problems.
More stuff, less freedom.
古代ローマの哲学者セナカの言葉に
「The slave owners owned by their slaves. (奴隷所有者は奴隷たちに所有されている。)
というものがあります。
新しい家を買うために、あなたが2つ目の仕事も始めないといけないのであれば、本当にあなたが新しい家を所有していることになるのでしょうか?
毎朝犬を散歩に連れていって、餌を与えて、トリマーへ連れていって、
果たして飼われているのは犬なのか、人間なのか?
おばあさんがあなたにくれたペンダント。
おばあさんはあなたにびくびく無くさないかなといつも心配で不安で残りの人生を過ごしてほしくてあげたつもりではないのではないでしょうか?
旅行先で撮った写真が見つからなくなって、友達をせめるあなた。
思い出は自分の中に記憶として残っている、これだけで充分なのではないでしょうか?
物理的な”もの”だけではなく
仕事や会社のサイズも必要以上に大きくしないことが
満足がいく持続可能なビジネスではないのか?ということを説明している「Company of One」という本も似ている考えです。
サイズアップが必ずしも正しいわけではない。
社員が増えることで、自分への責任が増えたり、教育に時間がかかったり、税金が増えたり、その他の問題がでてきたり。
もし今の仕事と今の収入で普通に生活できているのなら、なぜサイズアップする必要があるのか?
そんな考えに基づいた本です。
我々は皆自由で産まれたきたはずなのに
メディアや周りの影響、社会的プレッシャーから「自分の心地よい度」がどんどんと変わっていってしまうことも怖いポイントです。
例えば、掃除機ロボットルンバを買って使い始めると、ルンバなしの生活なんて考えられませんよね?
周りの影響や突破的な欲求でものを購入し、自分の自由を失うことを避けるよう気をつけたいものですね。
散歩
どんな場所にいて、どんな暮らしをしていても行うことができる「静けさ」に近づくことができる行動が散歩です。
カロリーを燃やすとか、〇〇キロ歩くなど、そんな目標やゴールを持たずにただただ歩く。
スマホも持たず、音楽も聞かずに足を進める。
頭も中を空っぽにする必要はありません。いろんな考えが浮かんできていいのです。
いろんな考え浮かんでいることを受け止めます。
たまにはいつもと違う道を歩いてみて、新しい発見があったり。
いつも通っている道に、綺麗な花を見つけてみたり。
この道を1,000年前はどんな人が歩いていたんだろうと妄想してみたり。
そんな散歩はある意味でお金のかからない贅沢かもしれません。
スマホのおかげで、どこにいても24時間外部とつながっていることが当たり前となった世界。
なかなか自分と向き合う時間をとることが難しくなってきました。
そんな時代だからこそ、散歩は外部からの連絡を経ち
自分と向き合う時間を作ることができる良い方法でもあります。
また歴史上の著名人をみてみても散歩愛好家が多いのも、偶然ではないはずです。
スティーブ・ジョブズ、アルバード・アインシュタイン、チャールズ・ダーウィン、イエス・キリスト、などなど。
一歩一歩体を動かす。この動きの繰り返しが脳への血液の循環を良くしてくれ、アイデアのひらめきへと導きます。
この散歩という贅沢を1日に少しでもいいので、自分に与えてみませんか?
まだまだこのブログではカバーできなかった内容も「Stillness is the Key」にはたくさんあります。
また人それぞれ響く部分も違うはずですし、同じ人でも時期が違うと響く部分も変わってくるはず。
きっとこれから10年、20年経った後でも、読み返すとまた新たな発見をくれそうなそんな本です。
ぜひ気になる方は自分でも読んでみてください。



















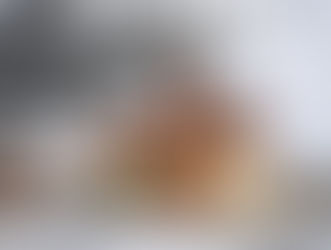







コメント