『ハマるしかけ』の著者が教える「集中力」の極意|『最強の集中力』実践ガイド
- ptakuyap15
- 2021年9月6日
- 読了時間: 23分
更新日:2025年2月25日

このブログは、Nir Eyal (ニール・イヤール)さんの「Indistractable」という本をもとにした記事です。
Nir Eyalといえば、多くのゲーム会社やアプリ会社のバイブルとなった、人を虜・アディクトにするにはどうすればいいのかを説明した、「Hooked(日本語名:ハマるしかけ 使われつづけるサービスを生み出す[心理学]×[デザイン]の新ルール)が有名です。そんな彼が逆にこういったアプリなどのテクノロジーに邪魔をされずに、本当に自分が集中したいことに集中するにはどうすればいいのか?そんなことを書いた本です。
目次:
『最強の集中力』とは?本の概要と著者Nir Eyalについて

Nir Eyalといえば、ベストセラーとなった 『Hooked(日本語名:ハマるしかけ 使われつづけるサービスを生み出す[心理学]×[デザイン]の新ルール』 の著者としても有名です。
この本では、ゲーム会社やアプリ開発者がユーザーを惹きつけ、離れられなくするための心理学とデザインの戦略が解説されていました。つまり、人々をテクノロジーに 「依存させる側」 の視点を持つ人物です。
そんなNir Eyalが今度は逆の視点から、スマホやSNS、通知の誘惑に邪魔されることなく、本当に集中すべきことに没頭するための戦略を解き明かしたのが『最強の集中力』。
現代の情報過多な環境の中で、戦略的に集中力をコントロールし、生産性を向上させるための実践的な手法が満載の一冊となっています。
気が散ることの真の原因
気が散るとは?本当の「障害」とは?
「よし、毎日仕事から帰ったら夜8時から英語の勉強をしよう!」
そう決めたはずなのに、スマホの通知が鳴り、「〇〇さんがあなたをフォローしました。」 というメッセージを見た瞬間、ついインスタを開いてしまう。気づけば夜10時になっていて、結局何も進んでいない…。
こんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか?
例えば、健康のために「毎日ランニングしよう!」と決意したり、留学のために「TOEFLの勉強をしなきゃ!」と計画を立てたり。ほとんどの人は「やるべきこと」が分かっています。
この本では、「自分がやると決めたこと」=Traction(トラクション) と定義しています。
対して、「それを邪魔するもの」=Distraction(ディストラクション/気を散らすもの・障害) と呼びます。
重要なのは、何が「障害」になるのかを知るためには、まず「Traction(本当にやるべきこと)」を明確にする必要がある ということです。
また、このTractionは状況によって変わることもあります。例えば、仕事中に「メールをすべて返信する」ことはTractionですが、週末に家族と食事をしている時にスマホでメールを見るのはDistractionになります。
つまり、何が集中を妨げる「障害」なのかは、自分が今どんな時間を過ごしたいのか によって変わるのです。
障害の原因
イェール大学教授の ゾーイ・チャンス(Zoe Chance) 氏は、TEDトークで自身が 万歩計アプリに依存した 経験を語っています。
このアプリは、友達と歩数を競い合えたり、歩くことで仮想通貨を獲得し、ゲーム内で買い物ができる仕組みになっていました。 ウォーキングがゲーム化 された感覚です。
健康のために使用していましたが、次第に 家族との時間を削ってまで歩くようになり、しまいには 寝る前に「あと〇〇歩でボーナスポイント!」の通知が来ると「あとちょっとだけ!」と歩き続け、気づけば深夜2時まで歩いていた ほどにのめり込んでしまいました。
この経験をもとに、彼女はTEDトークで 「行動を夢中にさせる仕組み」 について話しました。
語られなかった真実
しかし、このストーリーにはTEDトークでは語られなかった 隠れたポイント があったのです。
この話を聞いた ニール・イヤール 氏がゾーイ教授に直接話を聞いたところ、実は彼女が 万歩計アプリに没頭していた時期は、結婚や仕事で多くの問題を抱え、精神的にとても不安定な時期だったことが判明しました。
つまり、アプリの仕組みが依存性を高めたのではなく、彼女自身が現実のストレスから逃れる手段として、歩数を稼ぐことにのめり込んでいたのです。
つい 「SNSが悪い」「スマホが悪い」と思いがちですが、実はそれらが逃避先になっているだけの場合もあるのです。
行動の原理

朝起きてコーヒーを飲んだり、仕事帰りに駅でクロワッサンを買ってしまったり。こうした行動は、一見すると無意識に行っているように思えますが、実はすべて何らかの「きっかけ」(トリガー)によって引き起こされています。
「トリガー」と聞くと、例えば 焼きたてのクロワッサンの香りなど、外部からの刺激を思い浮かべるかもしれません。しかし、トリガーには「内部トリガー」(Internal Trigger)と 「外部トリガー」(External Trigger)の2種類があります。
内部トリガー(Internal Trigger)の例
・朝起きたばかりで頭がぼーっとしている → コーヒーを飲む
・金曜日の夜なのにひとりぼっちで寂しい → 友達に電話する
・肌寒く感じる → 上着を着るこれらは 自分の感情や身体的な状態によって引き起こされる行動です。
外部トリガー(External Trigger)の例
・スマホに「〇〇さんがあなたをフォローしました」という通知が届く → スマホを開く
・仕事中に同僚が「ランチ行こうよ!」と誘ってくる → 仕事を中断してランチに行く
・急に雨が降ってくる → 洗濯物を部屋に取り込む多くの場合、集中を妨げる要因(気を散らすもの) として注目されるのは 外部トリガーです。特に、スマホの通知やSNS、広告などテクノロジーの発展による外部トリガーの増加が、現代人の集中力を奪っていると言われがちです。
「気が散る」という現象は、昔から存在していた
しかし、私たちが 気を散らしてしまう原因は、何もスマホやアプリが登場してからの話ではありません。実は、人間はマンモスを狩っていた時代から「気を散らすこと」をしながら生きてきました。
例えば、狩猟採集時代の人間は、周囲の変化に敏感でなければ 生き延びることができませんでした。獲物を追っている最中でも、茂みの音や空の変化に注意を払わなければならなかったのです。
つまり、気が散るのは悪いことではなく、人間が生き残るために進化の過程で獲得した「本能」でもあるのです。
問題なのは、この本能が現代のテクノロジーによって過剰に刺激され、私たちの意図しない形で集中力を奪っていること。この仕組みを理解し、適切にコントロールすることが、「最強の集中力」を手に入れるための鍵となります。
気が散ることの真の原因
先ほどのゾーイさんの話に戻ります。果たして彼女が睡眠時間を犠牲にして万歩計に夢中になったのは、アプリの通知が原因だったのでしょうか?ゾーイさんは、実はプライベートで抱えていた様々な問題から来る不快感が真の原因だと、当時を振り返ります。
私もSNSに一番時間を浪費したのは、バリに移住した初期の頃だったかもしれません。誰も知らない土地で一人で、仕事中も基本的に1人だったので孤独を感じていました。この"疎外感"を紛らわせるために、SNSを過剰に利用していたのかもしれません。
重要なことに集中することを妨げる行動が"distraction"です。表面的にはテクノロジーが引き起こす外的なトリガーが原因に見えますが、実際の根本はあなたが抱える不快感にあります。孤独、苛立ち、緊張、疎外感などがそれです。
これらの不快感から逃れるために、あなたは"distraction"と呼ぶ行動を取るのです。この不快感、つまり内的トリガーこそが真の原因です。
この根本的な不快感に対処しない限り、外的トリガーを排除しても同じことが繰り返されます。したがって、この不快感とうまく付き合い、コントロールする方法を学ぶことで、皆さんも「最強の集中力」を身につけることができます。
不快感と付き合う方法
「不快感」の対処法
スマホやテクノロジーが集中力の欠如の原因ではなく、誰もが抱える「不快感」が真の原因であることが分かりました。この「不快感」に対して私たちができることは二つあります。
1. 「不快感」を消す方法を学ぶ。
2. 「不快感」と上手に付き合う方法を学ぶ。
ニールさんは、後者の方が効果的だと述べています。では、どうやって「不快感」と付き合っていけばいいのでしょうか?具体的な方法を紹介します。
方法1.科学者になり自分を観察
科学者になったつもりで考えてみましょう。研究対象はあなた自身です。研究者としては、公平な目線で、感情に流されずに研究に取り組んでください。
次回、あなたが障害だと感じる行動をしようとした時、その気持ちを観察してメモを取りましょう。
例えば、私の研究例を紹介します。たくやという動物がいて、健康になりたい、無駄遣いを減らしたいという目標がありますが、高頻度でピーナッツを衝動的に食べることが障害となっています。
見てください、またピーナッツを食べていますね。
感情を観察しましょう。この特別な虫メガネを使えば、動物の心が見えます。疲れた時やイライラしている時に食べていることがわかりました。イライラの原因は、長いミーティングに時間を取られることです。
アマチュアとプロの科学者の違いは、好奇心を持って研究することです。アマチュアは自分を責めがちですが、感情を入れずにプロとして取り組むべきです。
この研究を繰り返すことで、自分の習性が分かり、不快感の真の原因を知ることができます。不快感がわかれば、健康的な方法で解消しましょう。
疲労感を解消するためにしっかり睡眠を確保し、長いミーティングにイライラしているなら、効率的な進行方法を提案しましょう。これにより、障害の根本原因である不快感を解消できます。
方法2.衝動の波に乗る

「不快感」を完全に解消することは難しい場合もありますが、そんな時はどう対処すれば良いのでしょうか?
「不快感」は衝動を引き起こす原因となります。例えば、退屈さから仕事中に1分おきにツイッターをみたくなったり、上司が怖くて友人とのランチ中にLINEの返信が気になったりします。
このような衝動に対処するための方法は、波乗りのようなものです。
砂浜に立っているとき、遠くから近づいてくる波をイメージしてください。波は最初小さく、近づくにつれて大きくなり、再び小さくなります。衝動も同様で、最初は大きく感じても、我慢すれば次第に収まります。
2010年の実験で、喫煙するフライトアテンダントに勤務中の喫煙衝動についての調査があります。
被験者全員喫煙休憩前に衝動が最も強くなり、休憩中に喫煙した人も、我慢した人も結果的には衝動が同じレベルに減少したことが分かりました。このように、衝動の波にうまく乗ることで対処できます。
ある研究では、衝動の波に乗る訓練を7日間行うことで、喫煙者のタバコ欲求を37%減少させることにも成功しました。
この原理を応用した「10分ルール」も有効です。これは、衝動が起きたらまず10分待つという方法です。例えば、甘いものを避けているのにシュークリームが食べたくなった場合、10分間その衝動を待ち、10分後も食べたい気持ちが続くなら食べるというものです。
私もこの方法を試したことがありますが、10分待っている間に衝動を忘れてしまうことがほとんどでした。
方法3.川の流れのように
その他の衝動の対処法として、今度は川をイメージしてみましょう。
自分の目の前に大きなゆったりとした流れの川があります。
その川の上に大きな葉っぱが次々と流れています。桃太郎の桃のように。。
あなたの中に衝動が出てきたら、そっとこの葉っぱの上にその衝動をのせてあげましょう。
あなたの目の前をすぎさり右側に、そしてどんどんと小さくなってしまいにはみえなくなってしまいましたとさ。。おしまい。
というようにビジュアル化することで衝動に対処する方法もおすすめです。
Tractionを確保する方法
Distraction(障害)を削減する方法を理解できたら、次にTraction(本当にやるべきこと)をする時間を毎日確保していくことが必要です。
TO DOリストの危険性

「集中力がなくて困っている。スマホに邪魔されて生産性が低い。」という悩みを抱える人が多いです。そんな時、「何に集中しようとしているの?」と聞くと、無限に並ぶタスクリストを見せてくる人が少なくありません。これは、何をすべきかが不明確な状態です。
多くの人が「distraction (障害)」が何に対するものか曖昧で、その障害に邪魔されている自分を責めます。本当にやるべきこと“Traction”を明確にする必要があります。
ニール氏は、TO DOリストを基準にしたライフスタイルが危険であると警告しています。
TO DOリストに基づいて1日や1週間、さらには人生を評価することは危険です。なぜなら、TO DOリストは永遠に終わらないからです。私もタスクリストを使いますが、全てのタスクが完了したことはありませんし、完了した人にも出会ったことがありません。
忘れないためにタスクをリスト化することには賛成ですが、TO DOリストの完了度を評価基準にすることには反対です。
では、何を基準に"良い日"や"生産性の高い日"と評価すればよいのでしょうか?それは、「計画したことを、障害に邪魔されずにその時間に実行できたかどうか」を基準にすべきという考え方です。
多くの人が1日のスケジュールを組んでいるでしょうか?おそらく少数派です。自分の時間を守らなければ、他の誰かがあなたの時間を奪ってしまいます。上司や友人、SNSアプリやネットフリックスが知らないうちに時間を奪います。
古代ローマの哲学者セネカは2000年以上前に「人は個人的な資産には慎重だが、時間を無駄遣いする。時間こそが最も大切にすべきものである。」と述べています。
タイムボクシングを用いて1日のスケジュールをしっかりとブロックすることで、上記の基準で1日や1週間を評価できます。
タイムボクシング
では具体的にタイムボクシング(日程調整)の方法を紹介します。
日程調整は仕事だけのことをカレンダーに埋めていくのではなく、生活全ての出来事をカレンダーに埋めていく必要があります。
多くの方の1日は以下の3つの領域からなると思います。
1.健康 (自分自身の時間。睡眠や運動など) - 自分自身が健康でないと何もできません
2.人間関係 (家族や恋人、友人との時間) - 多くの研究で孤独が長生きの大きな敵であることが明らかになってきています。
3.仕事(仕事の時間) 自分の体が不健康でボロボロだと何もできないので、1が一番優先度が高いです。
なので、しっかりと睡眠時間や運動をする時間をまずはカレンダーで確保していくことが重要です。
ここで注意したいのが、「ネットフリックスでドラマを観ること」に罪悪感を感じる必要がないということです。
もちろんそれが元々計画された時間内の行動であれば、それはそれでグッドと評価されるべきです。
健康領域の時間を確保したら、次は2の人間関係の時間を確保します。
家族や恋人、友達と一緒にスポーツをしたり、映画を観たり。カフェに行ったり、そんな時間を確保します。
最後に3の仕事領域のタイムボクシングです。
仕事には大きく分けて2つの種類があると考えられています。
反応的作業 - メール返信、Teamsやスラックの返信、お願いされたタスクなど、外部に対しての反応として行う仕事。単発なタスクが多い。じっくり的作業 - デザイン作成、プロジェクト考案など、じっくりと集中して行うことができるタスク。クリエイティブなタスクが多い。フローに入りやすい。私自身を含め、多くの人が反応的作業でカレンダーが埋まっている人が多いと思います。
ニールさんは1日20分でもいいので、じっくり作業のための時間をブロックしていくことで、やりがい、幸せに繋がると主張しています。
また毎週15分でもいいので、自分のタイムボクシングを振り返る時間を設けましょう。
やると決めたことができたのか?
できなかった場合はその障害(distraction)は何だったのか?この障害を引き起こした不快感(内的トリガー)は何だったのか?
30分で足りると思っていたタスクが実は50分かかったことが分かったりもします。
そして3つの領域それぞれにどのくらい時間を費やしているかもみてみましょう。
タイムボクシングを行ってみての感想
実際に私もこのシステムを取り入れてみました。
良かった点
1.自分でコントロールできない結果(アウトプット)ではなく、コントロールできるインプットに集中する考え方を身につけることができた。
タイムボクシングの評価基準は、「やると決めたことをその時間にできた」なので「タスクを完了することができた」ではない。
もちろんタスクを1つ1つこなしていくことは大切ですが、一生懸命集中して取り組んでもタスクを完了できない時もあります。
そんな時に、「タスクをこなすと決めて完了できなかった自分はだめだ。」と自己批判に陥りがちです。
そうではなく、決めた時間に決めた行動・タスクを行えたのでグッドと、インプットを評価の指標にすることができます。
睡眠を例にとっても、「しっかりとした睡眠をとらなきゃだめだ」と変に自分にプレッシャーをかけてあえて睡眠の妨げになりがちです。
ところが、睡眠に割り当てた時間にしっかりとベッドに入ることができた、睡眠のための時間を確保することができた、それだけでGOODと振り切り、それでも眠りにつけなければ、自分の身体が睡眠を必要としていないだけだ、本でも読もう!と開き直る考え方もできます。
仕事以外のことに罪悪感を感じることなく時間を費やすことができる。
今までは海外ドラマを観たり、Youtubeのビデオを観た後に、生産性のないことをしてしまったと罪悪感を感じることが時々ありました。
しかし、あらかじめこのようなエンターテイメントの時間を確保することで罪悪感なく楽しむことができます。
悪かった点
タイムボクシングに時間がかかる
思った以上にタイムボクシングに時間がかかり、肝心なタスクや行動に遅れを取ってしまっている感がありました。
「こんなにタイムボクシングに時間をかけているけど、同じ時間でこのタスクをこなすことができたんじゃ。。」なんて思ってしまうことも多くありました。
予定通りにいかないことがストレスへ繋がる
毎週レビューをして改善していけばいいと言っても、なかなかスケジュール通りにいかないのが人生です。
仕事もそうですけど、特にドメイン1(You)とドメイン2(Relationship)が思い通りに行かないことが多いなあと感じました。
それはやはり、仕事だと他人に迷惑をかけるのでしっかりときちっと行う習性があるが、自分のこととなると、「まあ睡眠をちょっと削ってもいいや」と妥協してしまうことがありました。
また友達と一緒に時間を過ごしていても、つい長居をしてそれが自分のスケジュール通りにいかずストレスとなったり。。そんなこともありました。
また私の中で「Spontaneity (自発性)」というのも大事にしていきたいと考えています。
Spontaneityとはプランなしに気が赴くままに行動をすることです。
「よし、今日は天気がいいからちょっとウォーキングに行こう」
「映画の舞台となったギリシャのここに行こう!」とか。
こういったspontaneousな行動のおかげ体験できた素敵な経験がたくさん過去にあるからです。
spontaneous timeとかいう名目でそれもタイムボクシングしたり、、
いろんな方法を試しながら、自分にとって良いバランスを見つけていきたいです。
障害からあなたを守る3つの仕掛け
「不快感」が真の原因であることが分かった。「不快感」とうまく付き合い方法も分かった。
自分にとって重要なことに向かわせてくれる行動「Traction」を確保するタイムボクシングを理解した。
この全てを理解したあなたにとってきの最強の集中力3つの最終兵器シェアします。
ギリシャ神話 ユリシーズとセイレン

皆さんはギリシャ神話のセイレンについて聞いたことがあるでしょうか?
セイレン(Siren)は半身女性で、半身が鳥(のちに魚)の三人の姉妹で、鳥の翼を持ち、美しい歌声で船乗りたちを魅了するという生き物です。
この歌声を聞いた船乗りは、岩に船を衝突させて死んでしまう。と言われてそうです。
そんなセイレンの歌声に惑わされないために、ユリシーズは部下に耳栓をさせ、自分を船のマストに縛り付けるように命じました。
「セイレンの歌声を聴いて海に飛び込む。」という自分が起こしたくない行動を前もって強制的に予防したのです。
その結果、セイレンが現れて美しい歌声でユリシーズを誘惑しましたが、身動きが取れないおかげでセイレンたちを振り切ることができたそうです。
ユリシーズのように、私たちも将来の自分のために強制的な予防をあらかじめ仕掛けておくことで、distraction(障害)から自分を守ることができます。
では具体的な3つの仕掛けについてカバーしていきましょう。
1.手間をかけさせる仕掛け
認めたくないかもしれませんが、人間というのはlazy(怠惰)な生き物です。
これを逆手にうまく使った仕掛けがこれです。
私の経験をシェアします。しっかりと早起きをして熟睡するために私は10PMには眠りにつく、という習慣を身につけようとしていました。
しかし、これを妨げるのがスマホでした。
夜9時にはスマホを使うのをやめたいのだけど、夜9時半になっても終いには夜10時になってもスマホをやめられない。そんな障害に悩まされていました。
これをどんな仕掛けで攻略していったかというと、
夜9時にwifiの電源を全てオフにする、という仕掛けを加えました。
えっ?それだけ?でもwifiの電源なんてすぐにオンにできるじゃん!と思うかもしれません。
しかし、当時私の住んでいた部屋では、wifiのルーターはベッドの下にあり、少しベッドを動かさないと届かない位置にありました。
また電源を一度オフにすると、再度スマホにwifiが繋がるまで数分かかるようになっていました。
文字にしてみるととても僅かな手間に聞こえますが、
一度ベッドに入っている状態から、また一度ベッドからでて、さらにベッドを少し動かして、wifiをオンにする、
このことを考えると、自分のlazyさが勝り、もういいやとなってスマホを使うことを諦めることができました。
ここまでしなくとも、スマホを寝室ではない別の遠い部屋に置いたりするだけでも、この障害を手間で取っ払うことができます。
lazyな人間、hallelujah!!
2.金銭的な仕掛け
禁煙を成功させるために、お金を使ったある実験が行われました。
被験者を以下の3つのグループに分けます。被験者には禁煙を助ける全てのツールを無料で与えました。(ニコチンパッチなど)
何もしない。
6ヶ月間タバコを我慢できたら、650USDをあげるよ!
6ヶ月間タバコを我慢できたら、450USDをあげるよ!その代わり、150USDをチャレンジ前に回収します。チャレンジ失敗したら150USDは戻って来ません。チャレンジ成功したら150USD戻ってきます。
どのグループが禁煙成功率が一番高かったと思いますか?
3つの目のグループの成功率が最も高かった、という結果になったようです。
自分のお金が無駄になる。燃やされる。となると、人間はここまでも障害に強くなれるんですね。
家族やパートナーの力を借りて、この手法で障害から自分を守ることもできます。
例えば、毎日何かしらの運動をする、という習慣を身につけようとしていたとします。
あらかじめ嫁さんに1万円を預けておいて、1日サボるたびに1,000円ずつ子供のお菓子代に使わせる、という仕掛けを作ったり、、、
3.アイデンティティを使った仕掛け
意外と一番協力なのがこの仕掛けです。
「自分は健康志向の高い人間だ。」
「私は家族思いで愛妻家の夫だ。」
「私はフレンドリーなボスだ。」
皆さんもこのようなアイデンティティーを少なからずもっているはずです。
このアイデンティティーは、「こういう人でありたい」または「こういう風に他人からみられたい」という理想かもしれません。
そしてこういったアイデンティティーは3つのドメインにそれぞれに異なったアイデンティティーの場合もあるし、重なっている場合もあります。
アイデンティティーがどうであれ、このアイデンティティーを自分に毎日言い聞かせることで、そのアイデンティティーに反する障害を防ぐことができます。
1番いい例がベジタリアンやヴィーガンではないでしょうか?
ベジタリアンやヴィーガンの人は元々DNA的にそう産まれて来たのでしょうか?
きっとそうではなく、様々な理由で「ベジタリアン」「ヴィーガン」というアイデンティティーを確立したのだと思います。
私はお肉が大好きですが、過去に一度「1ヶ月ベジタリアンチャレンジ」をしたことがあります。
結果的にいうと思った以上簡単に成功したのですが、その成功の1番の鍵がこの「アイデンティティー」だったと思います。
「自分はベジタリアンだ。」と自分に言い聞かせ、そしてまた周りにも言い続けることで、アイデンティティーが確立されたのです。
マルチタスキング
メール返信をしながら会議に参加してみたり、友達の話を聴きながらインスタグラムのコメントに返事をしてみたり、掃除機をかけながらテレビを観たり、きっと多くの人が一度に複数のタスクをこなすマルチタスキングを試みたことがあるはずです。
結果的に両方のタスクが中途半端な結果になったり、あるいはばっちりと複数のタスクをこなすことができる人もいるかもしれません。
マルチタスキングは有効的なのでしょうか?
マルチタスキングは存在しない?
多くの研究や本で言われているのは、そもそもマルチタスキングなんて存在しない、ということです。
私たちの脳は一度に一つのことに行うようにしか作られていません。
「いやいや私はミーティングに参加しながら、写真の編集もできるよ!」
と感じる人もいるかもしれませんが、実はこれは10分の1秒という自分でも気づくことのできない素早さでタスクA(ミーティング)からB(写真編集)へとフォーカスをいったりきたり移し替えているだけなのです。
イメージとしてはスポットライトを当てる対象を瞬時に入れ変えているイメージです。
そういったこともあり、多くのプロダクティビティ関連の本やブログでは、「マルチタスキングはNG。プロダクティビティの敵。」と考えられることが多いです。
なぜかというと、幸福度にも深い関わりがあると言われるフローの状態に入りづらかったり、
「注意残余 attention residue」といって別のタスクに取り掛かる時に、前のタスクに、注意力が残ってしまい、注意力がしばらく分裂してからです。
マルチチャンネル・マルチタスキング
しかし、Nirさんはマルチタスキングは可能だと主張します。むしろマルチチャンネル・マルチタスキングという方法を取れば、もっと生産性が上がると言います。
マルチチャネル・マルチタスキングを説明するには、脳のリミットの仕組みを理解する必要があ理ます。
脳を大きなマルチ充電器とイメージしてみてください。
一つのタスクでたくさんのパワー(電気)を必要とする場合、他のタスクに使うパワーがなくなってしまう。
例:難易度の高い数学の問題を一度に2つ解くことができません。
脳からケーブルを通じて繋がっているチャンネルがあります。(下イメージでいうとスマホなど)

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚というチャンネルです。
このチャンネルの数も1種類につきひとつに限られています。なので2つのポッドキャストを片耳ずつ一度に聞くことはできません。
しかし、別々のチャンネル2つを一度に使うことはできます!
登山をしながらオーディオブックを聞くことができますよね。
実はこれは科学的な用語でCrossmodal Attentionといわれるように科学的に証明されていることのようです。
1つのチャンネルをオートパイロットで、他のチャンネルでフォーカス。
1つのチャンネルがパワーをめちゃくちゃ要するものでないかぎりうまくいくようです。
さらに面白いのが生産性をあげるだけでなく。学習能力をあげる組み合わせも研究でわかっているようです。
例えば、
聴覚チャンネルと視覚チャンネルを同時に使うことで、学習の質が上がる。ー>英語の発音を聞くよりも、スペルをみながらの方が覚えやすい。
ウォーキングをしながらの方が座っているよりオーディオブックに集中できる。
マルチチャンネル・マルチタスキングを利用した応用スキル
この方法を使って、自分がなかなかやり出せないことを身につけるようにハッキングすることができます。
ペンシルベニア大学で行われた実験では、ジムにいく習慣を身につけたい人を対象とした実験をしました。
「ハンガーゲーム」「トワイライト」など、続きが気になるようなオーディオブックのみが入ったiPodを準備し、ジムにいった時のみにしかこのiPodを使えないように制限したグループがそうでないグループと比べて51%多く、ジムにいって運動することができた、という結果になったようです。
このように自分が好きな行動を、自分がやらないといけないけどなかなかできない行動と結びつけることで、行動に結びつけることができます。






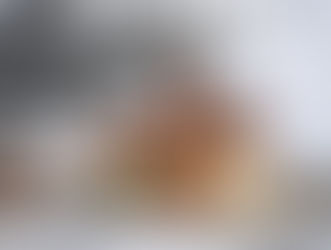




















コメント